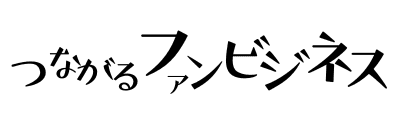「サンクスアイが行政指導を受けたって聞いたけど、何が問題だったの?」
「今もその会社の商品を使っていて大丈夫なの?」
SNSやニュースでサンクスアイの行政指導について目にして、不安や疑問を感じている方は少なくないでしょう。特に同社の製品を愛用している方や、MLM(マルチレベルマーケティング)業界に関心のある方にとって、正確な情報を知ることは非常に重要です。
結論から申し上げると、サンクスアイが受けたのは「行政処分」ではなく「行政指導」であり、法的な罰則や営業停止を伴うものではありません。しかし、消費者庁から具体的な改善要請があったことは事実であり、その内容と企業の対応を正しく理解する必要があります。
- 法的拘束力:なし
- 営業停止:なし
- 目的:改善の助言
- 罰則:なし
- 公表:任意
- 法的拘束力:あり
- 営業停止・罰金あり
- 目的:違反に対する制裁
- 法的根拠:景品表示法など
- 公表:必須
本記事では、消費者庁の公表内容をもとに、行政指導の背景から企業の再発防止策、現在の状況まで、中立的な視点で包括的に解説します。

ネットワークビジネスの合法性や安全な企業選びのポイントについても触れながら、読者の皆様が冷静に判断できる情報をお届けします。
サンクスアイとは?企業概要と事業モデル
行政指導の内容に入る前に、まずサンクスアイという企業の基本情報を整理しておきましょう。同社がどのような事業を展開し、どのようなビジネスモデルを採用しているのかを理解することで、行政指導の背景がより明確になります。
会社概要と沿革
株式会社サンクスアイは、健康食品や化粧品を中心に扱う企業として、2000年代初頭から事業を展開してきました。主に水素関連商品や健康補助食品、スキンケア製品などを取り扱っており、会員制の販売システムを採用しています。
同社は本社を日本国内に置き、全国に販売拠点や代理店ネットワークを持つ中堅規模の健康関連企業として知られていました。特に水素水や水素サプリメントといった製品が主力商品となっており、健康志向の高い消費者層をターゲットとしてきた背景があります。
主力商品とビジネス構造
サンクスアイの主力商品は以下のようなカテゴリーに分類されます。
健康食品分野では、水素関連サプリメント、酵素ドリンク、ミネラル補給食品などを展開。特に「水素」をキーワードにした製品群が中心的な位置を占めてきました。これらの商品は、健康維持や美容サポートを目的とする消費者に向けて販売されています。
化粧品・美容分野では、スキンケア製品やヘアケア製品なども取り扱っており、水素技術を応用したとされる美容商品もラインナップに含まれていました。
販売手法としては、直接販売と会員勧誘を組み合わせた形態を採用しており、会員が新たな会員を紹介することで報酬を得られる仕組みが存在します。この構造については、次のセクションで詳しく見ていきましょう。
ネットワークビジネス(MLM)との関係性
サンクスアイのビジネスモデルは、一般的に「ネットワークビジネス」または「MLM(マルチレベルマーケティング)」と呼ばれる形態に分類されます。
MLMとは、会員が商品を販売するだけでなく、新しい会員を勧誘することで報酬を得られる販売システムのことです。この仕組み自体は、特定商取引法で定められた要件を満たせば合法的なビジネスモデルとして認められています。
ネットワークビジネスとマルチ商法の法的な違いについては、合法と違法の境界線を詳しく解説した記事で詳細に説明していますので、MLMの基本構造を理解したい方はそちらも参考にしてください。
重要なのは、MLM自体が違法なわけではなく、運営方法や広告表現、勧誘手法によって問題が生じるケースがあるという点です。サンクスアイの行政指導も、まさにこの「運営方法の一部」に関する指摘だったのです。
サンクスアイに行政指導が行われた背景と経緯
それでは、サンクスアイが実際にどのような行政指導を受けたのか、その背景と経緯を時系列で整理していきます。ここでは消費者庁の公式発表や報道資料に基づいて、事実関係を明確にしていきます。
行政指導が発表された時期
サンクスアイに対する行政指導が公表されたのは、2018年3月のことでした。消費者庁は、同社の販売手法や広告表現に関して、景品表示法に基づく措置を講じる必要があると判断し、改善を求める行政指導を実施しました。
この時期は、健康食品業界全体で誇大広告や不適切な効能表示に対する監視が強化されていた時期と重なります。消費者庁は複数の企業に対して同様の指導を行っており、業界全体の適正化を図る動きの一環でした。
行政指導は公的な記録として残されており、消費者庁のウェブサイトや報道機関を通じて一般にも公開されています。これにより、消費者が企業の過去の対応を知る権利が保障されている点は重要です。
消費者庁の指摘内容
消費者庁がサンクスアイに対して指摘した主な問題点は、景品表示法における「優良誤認表示」に該当する可能性がある広告表現でした。
消費者庁の指摘ポイント(要約)
- 科学的根拠が不十分なまま健康効果を暗示する表現があった
- 消費者に誤解を与える可能性のある広告文言を使用していた
- 水素関連製品の効能表示が実証データを欠いていた
具体的には、商品の健康効果や効能について、科学的根拠が十分でないにもかかわらず、消費者に誤解を与える可能性のある表現が使用されていたことが問題視されました。特に、水素関連製品の効果について、実証されていない健康増進効果を暗示するような広告文言が確認されたとされています。
景品表示法では、商品やサービスの品質、効果について、実際よりも著しく優良であると誤認させる表示を禁止しています。健康食品業界では特に、「病気が治る」「痩せる」「若返る」といった断定的な表現や、医学的根拠のない効能の主張が規制の対象となります。
サンクスアイのケースでは、直接的な病気治癒の主張ではなかったものの、消費者が健康効果を過度に期待する可能性のある表現方法が用いられていた点が指摘されました。
指導の根拠となった事実と資料
消費者庁の行政指導は、複数の情報源に基づいて行われています。
まず、消費者からの相談や通報が一定数あったことが挙げられます。国民生活センターや各地の消費生活センターには、日々さまざまな消費者トラブルの相談が寄せられており、これらの情報は消費者庁にも共有されます。サンクスアイの製品や販売方法に関する相談が複数件寄せられていたことが、調査のきっかけの一つとなりました。
次に、企業が使用していた広告物やウェブサイトの表現が直接的な証拠となりました。消費者庁は、企業のホームページ、パンフレット、会員向け資料などを収集・分析し、景品表示法に抵触する可能性のある表現を特定しました。
また、商品の成分や効能に関する科学的エビデンスの有無も検証されました。健康食品の効果を広告する際には、その効果を裏付ける合理的な根拠が必要とされますが、サンクスアイの場合、一部の表現について十分な科学的根拠が示されていなかったことが確認されました。
これらの事実関係を総合的に判断した結果、消費者庁は行政指導という形で改善を求めることが適切だと判断したのです。
行政指導と行政処分の違いをわかりやすく解説
「行政指導」という言葉を聞いて、多くの方が「何か悪いことをした企業」というイメージを持つかもしれません。しかし、行政指導と行政処分は法的に全く異なるものであり、その違いを理解することが重要です。ここでは両者の違いを明確に説明します。
行政指導=「改善を求める注意」である
行政指導とは、行政機関が企業や個人に対して、法令違反を予防したり、自主的な改善を促したりするために行う指導や助言のことです。法的な強制力はなく、あくまで「このままだと問題になる可能性があるので、改善してください」という行政からのアドバイスという位置づけになります。
行政指導の特徴は以下の通りです。
法的拘束力がないという点が最大の特徴です。行政指導には法的な命令としての効力がないため、従わなくても直ちに罰則が科されることはありません。ただし、指導に従わず問題が継続した場合、より重い行政処分に発展する可能性はあります。
営業停止などの処分を伴わない点も重要です。行政指導を受けても、企業は通常通り営業を続けることができます。商品の販売停止や営業許可の取り消しといった措置は取られません。
公表の義務がない場合もあるという点も知っておくべきでしょう。行政処分の場合は必ず公表されますが、行政指導については、案件の重要性に応じて公表されることもあれば、非公表のまま企業に改善を求める場合もあります。
サンクスアイのケースは、消費者への注意喚起の意味も含めて公表された事例と考えられます。
行政処分との法的な違い
一方、行政処分とは、法令に基づいて行政機関が企業や個人に対して行う法的な処分のことで、行政指導とは性質が全く異なります。
行政処分の特徴を行政指導と比較すると、以下のような違いがあります。
| 項目 | 行政指導 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 法的拘束力 | なし | あり |
| 罰則 | なし | あり (罰金・営業停止など) |
| 公表 | 任意 (重要案件は公表) |
必須 |
| 企業への影響 | 軽微 (改善要請のみ) |
重大 (営業制限等) |
| 法的根拠 | 行政手続法 | 各個別法 (景品表示法など) |
| 不服申立 | 原則不可 | 可能 |
行政処分の例としては、「業務停止命令」「課徴金納付命令」「許可の取り消し」などがあります。これらは法的な効力を持ち、従わない場合はさらに重い罰則が科される可能性があります。
MLM業界における行政処分の事例や法的規制については、特定商取引法との関係を詳しく解説した記事でも触れていますので、より詳しく知りたい方はそちらもご覧ください。
行政指導の一般的な流れ
行政指導がどのように行われるのか、一般的な流れを理解しておくことも重要です。
第1段階:情報収集と調査 消費者からの相談、内部告発、定期的な市場調査などを通じて、行政機関が問題の可能性を把握します。サンクスアイの場合も、消費者からの相談や広告表現の調査から始まったと考えられます。
第2段階:事実確認 行政機関が企業に対して資料提出を求めたり、聞き取り調査を行ったりして、問題の有無を確認します。この段階で企業側の説明や証拠資料が検討されます。
第3段階:行政指導の実施 問題が確認された場合、まず行政指導という形で改善を求めます。指導内容は文書で通知されることが多く、具体的な改善点や期限が示されます。
第4段階:改善状況の確認 企業が改善措置を講じた後、行政機関がその内容を確認します。適切な改善が行われていれば、指導は終了となります。
第5段階:未改善の場合の対応 もし企業が行政指導に従わず、問題が継続する場合は、より強い措置である行政処分に移行する可能性があります。
サンクスアイのケースでは、行政指導を受けた後、企業側が改善措置を講じたため、より重い処分には至りませんでした。この流れを理解することで、「行政指導」が必ずしも企業の違法性を意味するものではなく、早期の改善を促すための手段であることがわかります。
サンクスアイの対応と再発防止への取り組み
行政指導を受けた後、サンクスアイがどのような対応を取ったのか、そして再発防止のためにどのような体制整備を行ったのかを見ていきましょう。企業の誠実な対応は、消費者の信頼回復において極めて重要な要素です。
公式コメントと謝罪内容の要約
サンクスアイは行政指導を受けた直後、公式ウェブサイトや会員向け通知を通じて、事態の説明と謝罪のコメントを発表しました。
その内容の要点は以下の通りです。
まず、消費者庁からの指導内容を真摯に受け止め、広告表現において消費者に誤解を与える可能性があったことを認めました。企業側は意図的な誤認表示を行ったわけではないものの、結果として不適切な表現が使用されていたことを謝罪しています。
次に、該当する広告物やウェブサイトの表現を速やかに修正・削除することを約束しました。具体的には、健康効果を過度に強調する表現や、科学的根拠が不十分な効能の記述を全面的に見直すとしています。
さらに、今後このような事態が起きないよう、社内体制の抜本的な見直しを行うことも表明しました。広告審査の強化、従業員教育の徹底、外部専門家による監査体制の導入などが具体策として挙げられています。
社内体制の見直しと外部監査の導入
行政指導後、サンクスアイは再発防止のために複数の組織的改革を実施しました。
広告審査部門の強化 新たに広告審査を専門に担当する部署を設置し、すべての広告物、ウェブサイトの文言、会員向け資料などを事前にチェックする体制を整備しました。これにより、景品表示法や薬機法に抵触する可能性のある表現が使用される前に、専門部署が精査する仕組みが確立されています。
法務・コンプライアンス部門の設置 企業内に法務専門の部署を新設し、常勤の法務担当者を配置しました。この部署は、日々の業務における法令遵守の確認だけでなく、社内規定の整備や従業員向け研修の企画なども担当しています。
外部専門家による定期監査 弁護士や消費者問題の専門家など、第三者の立場から企業活動をチェックする外部監査制度を導入しました。これにより、社内だけでは気づきにくい問題点や、業界の最新規制動向を取り入れた改善が可能になっています。
再発防止策の具体例
- 広告審査専門部署の設置
- Web・紙媒体の全チェック
- 会員向け資料の事前審査
- 表現ガイドラインの策定
- 法務専門部署の新設
- 常勤法務担当者の配置
- 社内規定の全面見直し
- コンプライアンス研修実施
- 外部監査制度の導入
- 弁護士による定期チェック
- 消費者問題専門家の助言
- 最新規制動向の取り入れ
- 定期研修プログラムの実施
- 景品表示法・特商法の教育
- 適切な商品説明の指導
- オンライン教育の導入
サンクスアイが実施した具体的な再発防止策をいくつか紹介します。
広告表現ガイドラインの策定 健康食品の広告に使用できる表現、使用できない表現を明文化したガイドラインを作成しました。例えば、「病気が治る」「必ず痩せる」といった断定表現の禁止、「個人の感想です」という注釈の義務化、科学的根拠のない効能主張の禁止などが詳細に規定されています。
社員・会員への教育プログラム 正社員だけでなく、販売活動に携わる会員に対しても、定期的な教育研修を実施しています。特に、景品表示法や特定商取引法の基本的な内容、適切な商品説明の方法、消費者とのコミュニケーションにおける注意点などが研修内容に含まれています。
商品説明資料の全面見直し 会員が販売活動に使用する商品説明資料をすべて回収し、法令に準拠した新しい資料に差し替えました。新資料には、商品の成分表示、適切な使用方法、注意事項などが明確に記載され、誤解を招く表現は徹底的に排除されています。
消費者相談窓口の充実 消費者からの問い合わせや苦情に迅速に対応できるよう、カスタマーサポート体制を強化しました。専用の相談窓口を設置し、消費者の不安や疑問に丁寧に応える体制を整えています。
これらの取り組みは、単に行政指導への対応というだけでなく、企業として長期的に消費者の信頼を得るための基盤づくりと位置づけられています。
サンクスアイの現在(2025年)の状況と信頼回復の進捗
- 水素関連製品の健康効果について科学的根拠が不十分
- 消費者に誤解を与える可能性のある表現
- 効能の過度な強調
- 不適切な表現の削除・修正
- 消費者庁への改善報告書提出
- 会員への注意喚起
- 広告審査専門部署の設置
- 広告表現ガイドラインの策定
- 全社員向けコンプライアンス研修
- 法務専門部署の新設
- 外部弁護士による定期監査開始
- 会員向けオンライン教育システム導入
- 過去資料の総点検完了
- 四半期ごとの外部監査実施
- 業界団体との連携強化
- 消費者相談窓口の充実
- 苦情件数の減少傾向を確認
- SNS・デジタル広告の監視強化
- AI活用による広告審査の効率化検討
- 透明性向上のための情報公開拡大
- 追加の行政処分なし(2025年10月現在)
行政指導から約7年が経過した2025年現在、サンクスアイの状況はどうなっているのでしょうか。企業の改善実績と現在の取り組みについて見ていきます。
行政指導以降の改善実績
2018年の行政指導以降、サンクスアイは段階的に改善を進めてきました。
まず、指導直後の2018年中に、指摘された広告表現の修正を完了し、消費者庁に改善報告書を提出しました。その後、追加の指導や処分は受けておらず、表面的には法令遵守体制が機能していると評価できます。
2019年から2020年にかけては、社内体制の整備期間として、前述の広告審査部門の設置や従業員教育プログラムの本格稼働が行われました。この期間に、過去に作成されたすべての広告物や会員向け資料の総点検も実施されています。
2021年以降は、改善体制の定着期として、定期的な外部監査の受審や、業界団体への加盟による自主規制の強化などが進められてきました。MLM業界全体でコンプライアンス意識が高まる中、サンクスアイも業界標準に沿った運営を心がけているとされています。
消費者対応と苦情件数の推移
企業の信頼性を測る一つの指標として、消費者からの苦情件数や相談内容の変化があります。
国民生活センターや各地の消費生活センターに寄せられる相談件数を見ると、行政指導直後の2018年から2019年にかけては、一時的に相談件数が増加しました。これは行政指導が公表されたことで消費者の関心が高まり、既存顧客からの問い合わせが増えたことが主な要因と考えられます。
しかし、2020年以降は相談件数が徐々に減少傾向に転じています。これは、広告表現の適正化や消費者対応の改善が一定の効果を上げていることを示唆しています。ただし、MLM業界全体として一定数の相談は常に寄せられており、サンクスアイについても完全にゼロになったわけではありません。
相談内容の質も変化しており、以前は「誇大広告」「効果がない」といった内容が多かったのに対し、近年は「解約方法」「返品手続き」といった手続き面での相談が中心となっています。これは、商品の宣伝方法は改善されたものの、MLMビジネスモデル自体に対する理解不足や不安は依然として存在することを示しています。
第三者監査の結果と今後の方針
サンクスアイは現在も定期的に第三者機関による監査を受けています。
外部監査では、広告表現の適法性チェック、販売手法の適切性評価、会員教育の実施状況確認などが行われています。監査結果は非公開が原則ですが、重大な問題が発見されていないことは、追加の行政指導や処分がないことからも推察できます。
今後の方針としては、以下の点が企業側から示されています。
デジタル広告への対応強化 近年はSNSやインターネット広告の重要性が増しており、これらの媒体での適切な表現管理がより重要になっています。サンクスアイも、デジタルマーケティングにおける法令遵守体制の強化を進めているとされています。
会員教育のオンライン化 コロナ禍を経て、対面での研修が困難になったことを受け、オンライン教育プラットフォームを導入しました。これにより、全国の会員が時間や場所を問わず、最新のコンプライアンス情報にアクセスできる環境が整備されています。
透明性の向上 企業情報や商品情報の公開範囲を拡大し、消費者が判断材料を得やすい環境づくりを進めています。ただし、MLM企業の性質上、報酬プランの詳細など一部の情報は会員向けにのみ開示されているのが現状です。
2025年現在、サンクスアイは行政指導以降、表面的には大きな問題を起こしていませんが、MLM業界全体への社会的な目は依然として厳しく、継続的な改善努力が求められている状況です。
サンクスアイのように行政指導を受けた企業の商品は安全?
ここまでの内容を踏まえて、読者の皆様が最も気になるであろう疑問に、Q&A形式で答えていきます。行政指導を受けた企業との付き合い方について、冷静に判断するための情報を提供します。
行政指導を受けた企業の商品を使っても大丈夫?
Q: サンクスアイの商品を現在使用していますが、健康被害の心配はありませんか?
A: 行政指導は主に「広告表現」に関するものであり、商品そのものの安全性に直接問題があったわけではありません。
サンクスアイの場合、指摘されたのは商品の効能を過度に強調する広告表現であり、商品に有害物質が含まれていたり、製造過程に問題があったりしたわけではありません。健康食品の安全性は、別の法律である食品衛生法によって規制されており、製造・販売には一定の基準をクリアする必要があります。
ただし、「広告で謳われていた効果が実際には期待できない可能性がある」という点は認識しておくべきです。行政指導の対象となった表現は、科学的根拠が不十分だったため問題視されたのですから、過度な期待は禁物です。
もし商品使用中に何らかの体調不良を感じた場合は、使用を中止し、医師に相談することをお勧めします。これはサンクスアイに限らず、すべての健康食品に共通する注意事項です。
Q: 行政指導を受けた企業から商品を購入することに不安があります。
A: 行政指導を受けたこと自体は、「過去に問題があったが改善を求められた」という事実です。重要なのは、その後の企業の対応と現在の状況です。
サンクスアイは指導後に複数の改善措置を講じており、追加の処分を受けていないことから、一定の改善は行われたと評価できます。ただし、それでも不安を感じるのは自然な感情です。
商品購入を検討する際は、以下の点を確認することをお勧めします。
- 現在の広告表現が適切かどうか(過度な効能を謳っていないか)
- 商品の成分表示が明確かどうか
- 返品・解約に関する説明が明確かどうか
- 消費者相談窓口が設置されているかどうか
また、同じ用途の製品は他の企業からも販売されているため、複数の選択肢を比較検討することも有効です。
今後も行政指導が続く可能性はある?
Q: サンクスアイは今後も行政指導を受ける可能性がありますか?
A: 可能性としてはゼロではありません。企業が法令遵守体制を整備していても、新しい広告手法の登場や法規制の変更により、予期せぬ問題が発生する可能性は常に存在します。
ただし、一度行政指導を受けた企業は、通常、再発防止に対する意識が高まります。サンクスアイも外部監査や社内体制の強化を進めており、少なくとも以前と同じような問題が繰り返される可能性は低いと考えられます。
MLM業界全体を見ると、行政指導や処分を受ける企業は定期的に出現しています。これは業界の特性として、個々の会員による広告活動のコントロールが難しいことも一因です。企業本体が適切な管理をしていても、一部の会員が独自にSNSで誇大広告を行うケースもあり、これが問題となることがあります。
消費者としては、企業の公式発表だけでなく、消費者庁のウェブサイトや消費生活センターの情報を定期的にチェックすることで、最新の状況を把握することができます。
Q: 他にも行政指導を受けたMLM企業はありますか?
A: はい、MLM業界では複数の企業が行政指導や行政処分を受けた実績があります。
過去には、ジャパンライフ(2017年に業務停止命令)、ケフィア事業振興会(2018年に破産)など、重大な処分を受けた企業も存在します。これらは行政指導よりも重い「行政処分」を受けた事例であり、サンクスアイのケースとは深刻度が異なります。
また、大手企業でも広告表現に関する行政指導を受けることはあり、業界の規模や知名度に関わらず、法令遵守が求められている現状があります。
MLM業界特有のリスクや、悪質な企業を見分けるポイントについては、ネットワークビジネスとは?わかりやすく仕組みとリスクを図解で解説で詳しく説明していますので、MLMビジネスへの参加を検討している方は事前にご確認ください。
安全な企業・サプリを選ぶには?
Q: 健康食品やサプリメントを選ぶ際、信頼できる企業を見分けるポイントは?
A: 信頼できる企業を見分けるためには、以下のチェックポイントを確認することをお勧めします。
企業情報の透明性 会社の所在地、代表者名、設立年、資本金などの基本情報が明確に公開されているかを確認しましょう。怪しい企業は連絡先が不明確だったり、頻繁に社名を変更したりする傾向があります。
広告表現の適切性 「病気が治る」「必ず痩せる」「副作用なし」といった断定的で過度な表現を使っている企業は要注意です。信頼できる企業は、科学的根拠に基づいた慎重な表現を使用し、「個人の感想です」「効果には個人差があります」といった注釈を適切に入れています。
第三者認証の有無 GMP(Good Manufacturing Practice:適正製造規範)認証を取得しているか、第三者機関による品質検査を受けているかなども重要な判断材料です。これらの認証は、製造工程や品質管理が一定の基準を満たしていることを示しています。
消費者対応の充実度 問い合わせ窓口が明確に設置されているか、返品・返金ポリシーが明示されているか、消費者からの質問に誠実に対応しているかなども、企業の信頼性を測る指標となります。
過去の行政処分歴 消費者庁のウェブサイトでは、過去に行政処分を受けた企業のリストが公開されています。気になる企業があれば、事前にチェックすることをお勧めします。ただし、行政指導歴がある企業でも、その後の改善状況によっては選択肢に含めることは可能です。
- 連絡先や所在地が不明確
- 「絶対に効く」「必ず儲かる」など断定的な表現
- 高額な初期費用を要求される
- 友人・知人への勧誘を強く求められる
- 返品・解約に関する説明が曖昧
Q: ネットワークビジネスの企業から商品を買うこと自体、リスクがあるのでしょうか?
A: ネットワークビジネス(MLM)自体は合法的なビジネスモデルであり、適切に運営されている企業から商品を購入すること自体にリスクはありません。
問題となるのは、以下のようなケースです。
- 商品の品質に見合わない高額な価格設定がされている場合
- 商品購入よりも会員勧誘に重点が置かれている場合
- 強引な勧誘や人間関係を利用した販売が行われている場合
- 「確実に儲かる」といった誇大な収益の約束がされている場合
純粋に商品が気に入って購入する分には問題ありませんが、「ビジネス参加」を勧められた場合は、慎重に判断する必要があります。特に、初期費用として高額な商品購入を求められたり、友人・知人への勧誘を前提とした説明を受けたりした場合は、一度立ち止まって考えることをお勧めします。
Q: サプリメントの効果がないと感じた場合、どうすればいいですか?
A: まず、商品のパッケージや公式サイトで推奨されている使用期間を確認しましょう。健康食品の効果は一般的に、数週間から数ヶ月の継続使用で評価されることが多いです。
短期間で効果が出ないからといって、すぐに「効果なし」と判断するのは早計な場合もあります。ただし、以下のような場合は使用を中止し、専門家に相談することをお勧めします。
- 体調不良や副作用と思われる症状が出た場合
- 明らかに広告と異なる状態である場合
- 適切な期間使用しても全く変化が感じられない場合
また、効果がないと感じた場合は、販売元に問い合わせることも有効です。信頼できる企業であれば、使用方法のアドバイスや返品対応について誠実に対応してくれるはずです。対応が不誠実だったり、返品を不当に拒否されたりした場合は、消費生活センター(電話番号:188)に相談することもできます。
サプリメントはあくまで「補助」であり、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠といった基本的な健康習慣の上に成り立つものであることも忘れないでください。
よくある質問(FAQ)
-
2018年3月に消費者庁がサンクスアイに対して実施した、景品表示法に基づく改善要請のことです。商品の健康効果について科学的根拠が不十分な広告表現が使用されていたことが指摘されました。行政指導は法的処分ではなく、企業に自主的な改善を促す措置です。
-
行政指導は法的拘束力のない「改善の要請」であり、罰則や営業停止を伴いません。一方、行政処分は法的効力を持ち、業務停止命令や課徴金納付命令などの重い措置が取られます。サンクスアイが受けたのは行政指導であり、行政処分ではありません。
-
行政指導は主に広告表現に関するものであり、商品そのものの安全性に問題があったわけではありません。健康食品の安全性は食品衛生法で規制されており、製造・販売には基準のクリアが必要です。ただし、広告で謳われていた効果が実際には期待できない可能性がある点は認識しておくべきです。
-
サンクスアイは指導後、広告表現の修正、広告審査部門の新設、外部監査の導入、従業員・会員への教育プログラム実施など、複数の再発防止策を講じました。また、消費者相談窓口の充実や広告表現ガイドラインの策定も行い、法令遵守体制を強化しています。
-
MLM(マルチレベルマーケティング)自体は、特定商取引法の要件を満たせば合法的なビジネスモデルです。違法となるのは、誇大広告、強引な勧誘、不当な契約条件などの問題がある場合です。サンクスアイもMLM形態を採用していますが、ビジネスモデル自体が違法なわけではありません。
-
主なポイントは3つです。①企業情報の透明性(所在地、代表者名、連絡先が明確)、②広告表現の適切性(過度な効能を謳っていない)、③第三者認証の有無(GMP認証など)。また、消費者庁のウェブサイトで過去の行政処分歴を確認することも有効です。
-
まず推奨される使用期間(通常は数週間から数ヶ月)を確認しましょう。短期間で判断するのは早計です。それでも効果が感じられない場合や体調不良が出た場合は使用を中止し、販売元に問い合わせるか、消費生活センター(電話188)に相談することをお勧めします。
-
2018年の行政指導以降、サンクスアイは追加の指導や処分を受けておらず、表面的には改善体制が機能していると評価できます。消費生活センターへの相談件数も2020年以降は減少傾向にあります。ただし、MLM業界全体への社会的な監視は続いており、継続的な改善努力が求められています。
まとめ|信頼できる企業を見分ける3つのポイント
ここまで、サンクスアイの行政指導について、その背景から企業の対応、現在の状況まで詳しく見てきました。最後に、この事例から学べる「信頼できる企業を見分けるポイント」をまとめます。
この記事の要点まとめ
- サンクスアイの行政指導は「広告表現」が原因であり、法的処分ではない
- 企業は再発防止に向け、広告審査・教育・監査の三本柱を整備
- 2025年現在、追加の指導はなく、改善が定着している
情報公開と透明性
信頼できる企業の第一の条件は、情報公開の姿勢です。
企業の基本情報、代表者の氏名、事業内容、商品の成分表示など、消費者が判断に必要な情報を積極的に公開している企業は、透明性が高く信頼に値します。反対に、情報が曖昧だったり、問い合わせても明確な回答が得られなかったりする企業には注意が必要です。
特にMLM企業の場合、報酬プランの仕組み、会員の平均収入、成功率などのデータが公開されているかどうかも重要なチェックポイントです。「誰でも簡単に稼げる」といった抽象的な表現しかなく、具体的なデータが示されていない場合は、慎重に判断すべきです。
また、過去に行政指導や処分を受けた企業については、その事実を隠さず、改善策とともに公表している企業の方が、誠実な姿勢と評価できます。サンクスアイも公式サイトで行政指導の事実と対応を説明していますが、このような透明性は重要な判断材料となります。
再発防止策の有無と実効性
問題が起きた後、企業がどのように対応したかは、その企業の本質を映す鏡です。
行政指導を受けた企業が、単に表面的な修正だけで済ませているのか、それとも抜本的な体制改革を行っているのかは、大きな違いです。サンクスアイの場合、広告審査部門の新設、外部監査の導入、従業員教育の強化など、複数の具体的な対策を実施している点は評価できます。
ただし、これらの取り組みが形だけのものでないか、実際に機能しているかどうかを見極めることも重要です。その指標として、行政指導後に同じような問題が繰り返されていないか、消費者からの苦情が減少傾向にあるかなどを確認することができます。
企業のウェブサイトで「コンプライアンス方針」や「品質管理体制」について説明されているか、第三者認証を取得しているかなども、実効性のある再発防止策が取られているかを判断する材料になります。
第三者評価と客観的な情報の確認
企業の自己申告だけでなく、第三者による客観的な評価を確認することも大切です。
消費者庁や国民生活センターのウェブサイトでは、企業に対する行政処分の情報や、消費者トラブルの事例が公開されています。気になる企業がある場合は、事前にこれらのサイトで情報を検索することをお勧めします。
また、業界団体への加盟状況も一つの指標です。日本訪問販売協会やダイレクトセリング協会など、業界団体に加盟している企業は、団体の自主規制基準を遵守することが求められるため、一定の信頼性の目安となります。
さらに、第三者機関による品質認証(GMP認証、ISO認証など)を取得しているかどうかも重要です。これらの認証は、製造工程や品質管理体制が国際的な基準を満たしていることを示すものです。
インターネット上の口コミや評判も参考になりますが、極端に肯定的な意見や否定的な意見だけでなく、中立的で具体的な情報を提供している声を重視することが大切です。
最後に
サンクスアイの行政指導は、健康食品業界、特にMLM業界における広告表現の適正化という課題を浮き彫りにした事例でした。行政指導自体は法的処分ではなく、改善を促すための措置ですが、消費者としては企業がその後どのように対応し、信頼回復に努めているかを見極めることが重要です。
どの企業の商品を選ぶかは、最終的には消費者一人ひとりの判断です。しかし、その判断を行うためには、正確な情報と冷静な視点が不可欠です。本記事が、読者の皆様が健康食品やMLM企業と向き合う際の参考になれば幸いです。
健康は人生の基盤です。商品選びにおいても、広告の言葉だけでなく、企業の実態、成分の科学的根拠、自分の体質との相性など、多角的な視点から判断することをお勧めします。
もっと詳しく知りたい方へ
MLMビジネスの仕組みや法的規制についてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。
記事監修について
本記事は、消費者庁の公表資料、特定商取引法、景品表示法などの公的情報に基づいて作成されています。ただし、法的判断については個別のケースにより異なる場合がありますので、具体的な問題については専門家にご相談ください。
免責事項
本記事の情報は2025年10月時点のものです。法規制や企業の状況は変化する可能性がありますので、最新情報については各公的機関や企業の公式サイトでご確認ください。また、本記事は特定の企業や商品を推奨または否定するものではなく、客観的な情報提供を目的としています。
参考情報